災害に備える通信インフラとは?
-携帯電話がつながらない災害時に事業継続を支える通信方法
公開日:2025/01/31 更新日:2025/06/05
公開日:2025/01/31
更新日:2025/06/05
大規模災害が起きると、電話やインターネットをはじめとした複数の通信手段にアクセスが集中し、回線の混雑や停電などの影響で情報のやり取りが難しくなることがあります。近年の実例では、地震や台風時にスマートフォンでの通話やデータ通信が規制され、被災者同士や救援機関との連携といった必要な情報が届かない状態に陥ったケースがありました。
総務省や通信事業者は、災害時に通信障害が発生した場合でも、早期に復旧できる動員体制や移動電源車、ICTユニットを活用しています。しかし、現場での復旧までには時間がかかることも多く、緊急時には普段使いのネットワークが利用困難になる可能性があります。
そのため、災害時でも事業継続を可能にするためには、平時から信頼性の高い通信インフラを整備しておくことが重要です。このコラムでは、緊急時の通信が途絶えた際に代替手段や災害に備えた通信インフラの選択肢をご紹介し、企業が取るべき対策について考察します。

- 目次
- 災害時、なぜ携帯電話はつながらなくなるのか
- 原因①:通信混雑(輻輳)
- 原因②:基地局の被災・停電
- 災害時に「固定電話」も安心とは限らない
- 災害時に備えた「別の通信手段」が必要
- クラウド電話が災害に強い理由
- 災害時に利用可能な通信手段と特徴
- SNSやインターネット通信手段
- 公衆電話の利用とその重要性
- 特別な通信デバイス
- 00000JAPANと特設公衆Wi-Fiの使い方
- 企業が事業を止めないために必要な「通信BCP」
- Widefoneが提供するBCP対策
- クラウド型で拠点間連携を強化
- 携帯回線に依存しない代替通信手段
- Widefoneと他社クラウド電話との比較
- まとめと今後の災害通信への対応
災害時、なぜ携帯電話はつながらなくなるのか
災害時には、安否確認や救助要請など、通信が生命線となる場面が多々あります。しかし、被災地では携帯電話がつながらない状況が発生することが少なくありません。その結果、必要な情報伝達が滞り、支援や避難行動に支障をきたす恐れがあります。こうした通信障害の背景には、さまざまな課題が存在します。ここでは、主な原因である「通信混雑」と「基地局の被災」について、それぞれ詳しく見ていきます。
原因①:通信混雑(輻輳)
災害発生直後は、多くの人が一斉に電話やインターネットを利用しようとします。これによりネットワークの処理能力を超えた「通信の渋滞」=輻輳(ふくそう)が発生します。
通信事業者はネットワーク全体の安定運用を守るため、一時的に通話制限や接続制御を行うことがあります。この制御では、緊急通報や行政機関向けの通信が優先されるため、一般ユーザーの通話やネット接続が制限されることがあるのです。
原因②:基地局の被災・停電
もう一つの大きな原因が、通信を支える基地局自体が被災するケースです。
地震や台風により設備が損傷したり、停電によって電源供給が絶たれたりすると、基地局は機能を失います。
多くの基地局には予備電源がありますが、稼働時間には限界があり、復旧には時間がかかるのが現実です。その結果、被災地域では携帯電話が全く使えない、という事態も起こり得ます。
災害時に「固定電話」も安心とは限らない
携帯電話の通信障害が注目されがちですが、実は固定電話にも課題があります。
確かに固定電話は「安定した通信手段」として認識されることが多いものの、災害時には停電や設備被災の影響を大きく受けやすいという弱点があります。
たとえば、オフィスや家庭に設置されている固定電話回線が断線した場合、通信は完全に遮断されます。さらに、停電時には電力供給が絶たれ、電話機が動作しなくなるケースも少なくありません。
また、固定電話はその名の通り設置場所が固定されているため、避難や外出先での使用ができないという制約もあります。これでは、非常時に柔軟な連絡手段として機能しづらいのが現実です。
災害時に備えた「別の通信手段」が必要
携帯電話や固定電話に依存しすぎることは、災害時における通信リスクを高める要因になります。
企業や組織においては、非常時でも確実に連絡が取れるよう、クラウド型の通話手段や、BCP(事業継続計画)に基づいた通信インフラの整備が求められます。
- 「基地局が使えない」
- 「電話が混雑してつながらない」
こうした事態に備えるためには、どこにいても利用できる通信手段が欠かせません。
たとえば、インターネット環境さえあればスマホやPCで会社番号の発着信が可能なクラウド電話は、災害時の強力なバックアップになります。
クラウド電話が災害に強い理由
「クラウド電話は災害に強い」とされる理由は、以下のような設計上の特長にあります。
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| クラウド保存 | データがクラウドにあるため、端末や設備が被災しても他拠点から利用可能 |
| インターネット通話 | 固定回線に依存せず、地域限定の物理的被害に左右されにくい |
| モバイル対応 | スマホ・タブレットから通話・設定が可能。避難先や自宅でも利用可能 |
最大の課題は、インターネット回線への依存です。クラウド電話はクラウドサーバーを通じて通信を行うため、災害時にインターネット回線が途絶えると利用できなくなる可能性があります。また、停電が発生した場合、Wi-Fiルーターや関連機器の電源が失われ、クラウド電話システム全体が機能しなくなるリスクがあります。
ただし、多くのクラウド電話サービスでは、複数のクラウドサービスや地理的に分散されたデータセンターを活用することで、災害時のリスクを最小限に抑える工夫がされています。このような設計により、特定の地域でインターネット回線やデータセンターに障害が発生しても、他の拠点でサービスを継続できる冗長性を確保しています。
また、自動的に別のサーバーへ切り替える仕組みや、モバイル通信を利用した代替手段を提供するサービスもあり、通信の安定性を高めています。
災害時に利用可能な通信手段と特徴

災害時の通信手段として携帯電話や固定電話だけに依存することには、これまで見てきた通り、多くのリスクが伴います。そこで、携帯電話がつながらない状況でも事業を継続するために役立つ、代替通信手段や効果的なソリューションについて詳しく見ていきましょう。
SNSやインターネット通信手段
電話回線が混雑しやすい災害時でも、テキストベースの通信(SNS・LINEなど)は比較的つながりやすい傾向があります。
これは、通話に比べて通信容量が小さく、ネットワークへの負荷が少ないためです。
| 通信手段 | 特長 |
|---|---|
| SNS(X、Facebookなど) | 状況共有や安否確認に便利。多人数に同時送信できる |
| メッセージアプリ(LINE等) | 通話不可でもテキスト送信が可能な場合がある |
公衆電話の利用とその重要性
意外に思われるかもしれませんが、公衆電話は災害時に極めて有効な通信手段です。
携帯のバッテリー切れや輻輳時でもつながりやすく、自治体によっては大規模災害時に無料化されることもあります。日頃から最寄りの公衆電話の位置を確認しておくことが重要です。
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| 高い通信安定性 | 回線が独立しており、災害時も利用できることが多い |
| 無料利用の可能性 | 災害時に通話料金が免除されるケースがある |
特別な通信デバイス
企業や自治体、医療機関などでは、一般回線とは異なる通信手段を非常時用に備えているケースもあります。
| デバイス | 特長 |
|---|---|
| IP無線機 | ・インターネット経由で広域通信/GPS連携も可能 ・災害時の位置情報共有に有効 |
| 衛星電話 | ・通信衛星を使用。地上回線に依存せず通信が可能 ・通話料・端末コストが高額 |
これらは日常利用には向きませんが、緊急時に確実な通信手段としての信頼性は非常に高いため、BCPや防災対策の一環として導入を検討する企業・団体が増えています。
00000JAPANと特設公衆Wi-Fiの使い方
大規模災害時には、携帯電話各社が共同で「00000JAPAN」という無料のWi-Fi接続サービスを開放することがあります。パスワード不要で利用できるため、早急にインターネットに接続して情報収集や連絡を取ることが可能です。また、自治体や民間施設が特設公衆Wi-Fiを設置する場合もあり、避難所や公共施設などで複数の通信手段が確保される体制を整えています。
企業が事業を止めないために必要な「通信BCP」
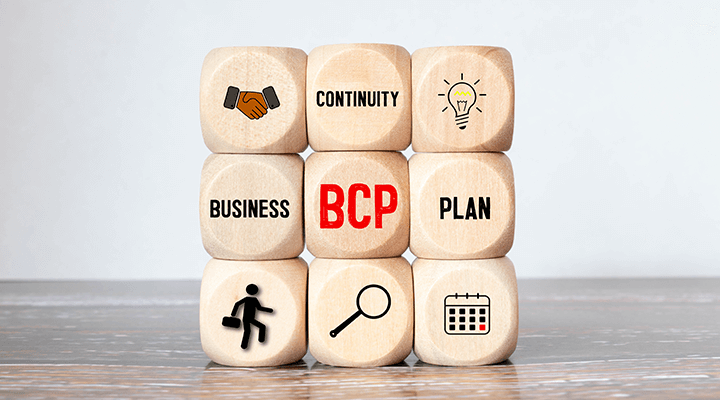
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策とは、災害や緊急時に事業を継続または迅速に復旧させるための計画や取り組みのことです。その中でも特に重要なのが、「通信手段の確保」です。
地震・台風・停電などによって、オフィスの固定電話や携帯電話が使えなくなると、顧客や取引先との連絡が断たれ、業務が大きく停滞してしまいます。その対策として有効なのが、インターネット回線を活用したクラウド型の電話システムです。クラウド電話であれば、特定の場所や設備に縛られず、災害時でもスムーズな業務継続が可能になります。
通信BCPは、企業の信頼を守るだけでなく、社員や関係者の安全と安心を確保するための“備え”でもあります。
Widefoneが提供するBCP対策
クラウド電話「Widefone」(ワイドフォン)は、災害時にも事業継続を支える柔軟で信頼性の高い通信ソリューションを提供します。スマートフォンを活用したクラウド型電話システムにより、オフィス外や災害時でも代表番号の着信や内線通話が可能です。これにより、事業の中断を最小限に抑え、迅速かつ効率的な対応を実現します。WidefoneのBCP対策がどのように役立つのか、詳しくご紹介します。
クラウド型で拠点間連携を強化
クラウド電話の最大の利点は、物理的な設備に依存せず、どこからでも通信が可能である点です。
インターネット回線さえあれば、オフィスが被災しても、別拠点や自宅から代表番号を使った発着信が可能になります。
たとえば本社が災害で機能停止した場合でも、支社や在宅勤務の社員が本社番号宛の着信を遠隔で受けることができるため、通信断絶による業務停止リスクを回避できます。
拠点間連携のクラウド活用例
| 状況 | クラウド電話の対応 |
|---|---|
| 本社が被災・停電 | 支社や在宅勤務者が代わりに代表番号で応答できる |
| 通常業務時 | 全国拠点で内線通話・転送がスムーズに行える |
| 地理的分散リスクの軽減 | データはクラウド上に保管、物理拠点に依存しない |
Widefoneを導入することで、災害時にも強い通信インフラを確保し、拠点間の連携を維持したまま事業継続が可能となります。
携帯回線に依存しない代替通信手段
Widefoneは、スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、050番号などの“予備用ビジネス番号”を持たせることが可能です。携帯回線が混雑や障害でつながらない場合でも、インターネット経由で安定した通話が確保できます。
安否確認や緊急連絡も、アプリからすぐに発信・着信が可能なため、通信断絶のリスクを減らし、スムーズな情報共有を実現します。
Widefoneの災害時通話イメージ
| 通信手段 | 状況 | 通信確保の可否 |
|---|---|---|
| 携帯電話回線 | 輻輳(混雑)や電波障害で不安定 | 利用不可の可能性あり |
| Widefone(IP通話) | インターネット環境があれば利用可能 | 代替通話手段として有効 |
加えてWidefoneは、上記のように災害に関するBCP対策だけではなく、携帯電話キャリアの大規模通信障害の備えとしても、大いに活用いただけます。日常使いが災害時のバックアップにつながるその理由を、過去の災害や障害をもとにご紹介している、以下の活用事例もあわせてご参考ください。
Widefone活用事例:見落とされがちな災害時の音声通信手段の備えは充分ですか?BCP対策にもWidefone
Widefoneと他社クラウド電話との比較
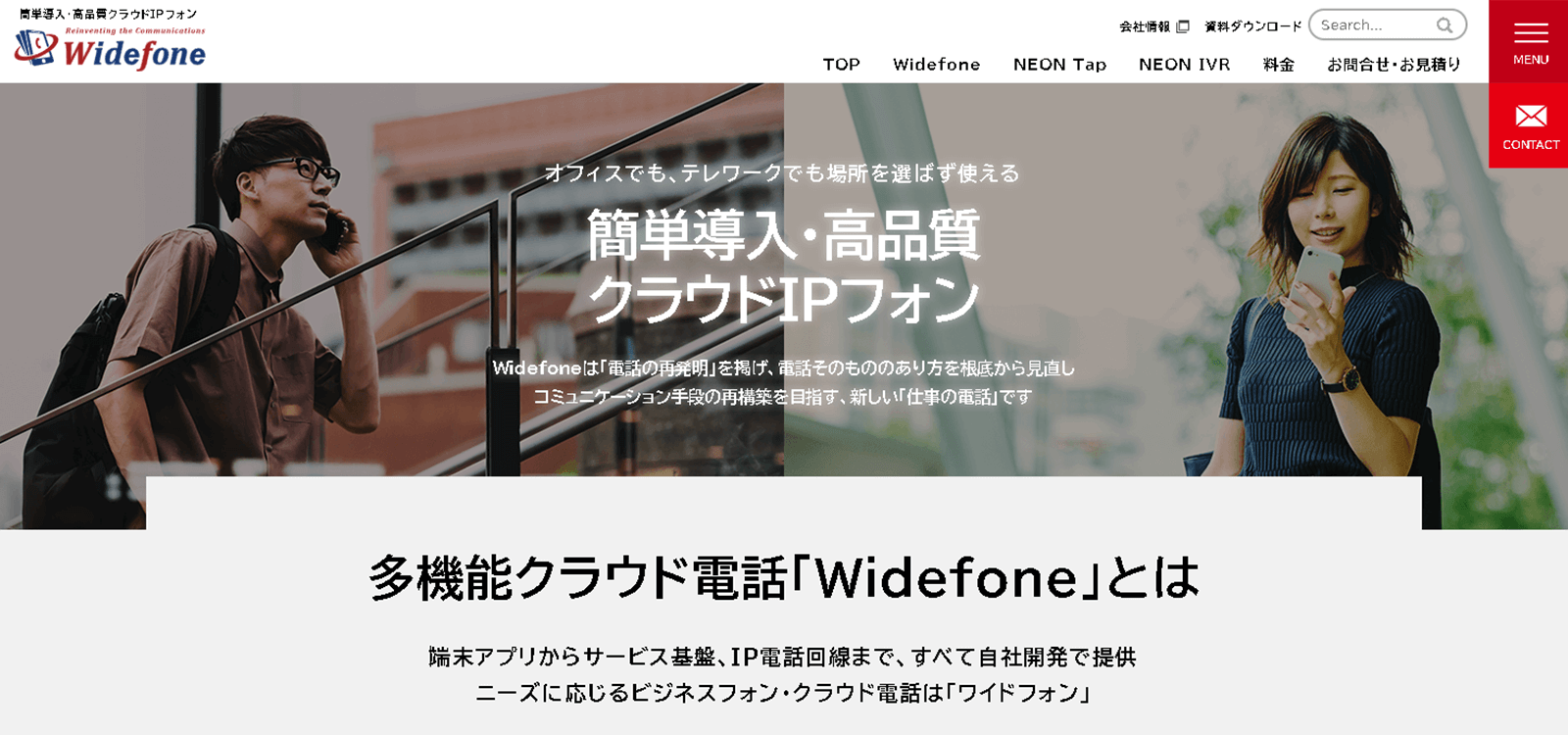
災害に強いと言われるクラウド電話ですが、提供サービスは複数あります。その中でWidefoneは他社にない以下のような特長を持っています。
- 専門性の高い通話アプリ
多くの同様製品が汎用的なプラットフォームをもとに設計されている中で、使いやすさを追求しゼロから設計したオリジナルアプリを提供しています。自社開発・自社運用サービスのため、お客様の声を反映したスピーディな機能開発が特長です - 豊富な機能
他社がオプションとして用意している「時間外スケジュール機能」や「不在着信メール通知機能」は標準機能として提供。オプションで選べる通話録音機能やSaaS型IVR機能も、お手軽な価格で提供しています。豊富な機能を手軽に使えることも、Widefoneの特長です - 導入と運用が手軽
予備用電話番号を持ちたいというご要望には、月額基本料金(900円)の費用対効果の高さも魅力の一つです。また、Widefoneどうしは通話が無料なので、社内の連絡や拠点間のやり取りがコストを気にせず行えます。
まとめと今後の災害通信への対応
災害に備え、そして実際に起こった際にどのように通信手段を活用し、情報を共有していくのか、最後に重要なポイントを整理します。
災害時通信では、多様な手段を事前に把握し準備しておくことが、回線輻輳や停電などのリスクを軽減する最善策となります。携帯電話や公衆電話、SNS、衛星電話などを状況に合わせて使い分け、安否確認や救援依頼を確実に行うための手順をあらかじめ取り決めておくと良いでしょう。通信事業者や自治体が行っている取り組みにも注目し、官民が連携して災害復旧を迅速化する動きに参加することで、社会全体の防災力が高まっていきます。
大規模災害はいつ発生するか予測が難しい一方で、通信インフラを守り支援する仕組みは日々進歩しています。今後も5Gや6Gなどの高速通信、AIやIoTを活用した被害最小化対策など、新しい技術が続々と登場するでしょう。私たち自身も災害時通信の基礎知識を身につけ、身近で使える手段を常に確認・アップデートすることで、万が一の状況にも慌てず行動できる態勢を整えることが大切です。
そして、災害時でも柔軟に対応できる通信手段として、クラウド電話の導入を検討することも有効です。その際は、高い柔軟性と経済性を兼ね備えたWidefoneを、ぜひ選択肢の一つに加えてください。
※機能や価格は公開日時点の情報です
※価格は税抜表示です
ビジネスフォンお悩み相談室
災害に備える通信インフラとは?
-携帯電話がつながらない災害時に事業継続を支える通信方法
公開日:2025/01/31 更新日:2025/06/05
公開日:2025/01/31
更新日:2025/06/05
大規模災害が起きると、電話やインターネットをはじめとした複数の通信手段にアクセスが集中し、回線の混雑や停電などの影響で情報のやり取りが難しくなることがあります。近年の実例では、地震や台風時にスマートフォンでの通話やデータ通信が規制され、被災者同士や救援機関との連携といった必要な情報が届かない状態に陥ったケースがありました。
総務省や通信事業者は、災害時に通信障害が発生した場合でも、早期に復旧できる動員体制や移動電源車、ICTユニットを活用しています。しかし、現場での復旧までには時間がかかることも多く、緊急時には普段使いのネットワークが利用困難になる可能性があります。
そのため、災害時でも事業継続を可能にするためには、平時から信頼性の高い通信インフラを整備しておくことが重要です。このコラムでは、緊急時の通信が途絶えた際に代替手段や災害に備えた通信インフラの選択肢をご紹介し、企業が取るべき対策について考察します。

- 目次
- 災害時、なぜ携帯電話はつながらなくなるのか
- 原因①:通信混雑(輻輳)
- 原因②:基地局の被災・停電
- 災害時に「固定電話」も安心とは限らない
- 災害時に備えた「別の通信手段」が必要
- クラウド電話が災害に強い理由
- 災害時に利用可能な通信手段と特徴
- SNSやインターネット通信手段
- 公衆電話の利用とその重要性
- 特別な通信デバイス
- 00000JAPANと特設公衆Wi-Fiの使い方
- 企業が事業を止めないために必要な「通信BCP」
- Widefoneが提供するBCP対策
- クラウド型で拠点間連携を強化
- 携帯回線に依存しない代替通信手段
- Widefoneと他社クラウド電話との比較
- まとめと今後の災害通信への対応
災害時、なぜ携帯電話はつながらなくなるのか
災害時には、安否確認や救助要請など、通信が生命線となる場面が多々あります。しかし、被災地では携帯電話がつながらない状況が発生することが少なくありません。その結果、必要な情報伝達が滞り、支援や避難行動に支障をきたす恐れがあります。こうした通信障害の背景には、さまざまな課題が存在します。ここでは、主な原因である「通信混雑」と「基地局の被災」について、それぞれ詳しく見ていきます。
原因①:通信混雑(輻輳)
災害発生直後は、多くの人が一斉に電話やインターネットを利用しようとします。これによりネットワークの処理能力を超えた「通信の渋滞」=輻輳(ふくそう)が発生します。
通信事業者はネットワーク全体の安定運用を守るため、一時的に通話制限や接続制御を行うことがあります。この制御では、緊急通報や行政機関向けの通信が優先されるため、一般ユーザーの通話やネット接続が制限されることがあるのです。
原因②:基地局の被災・停電
もう一つの大きな原因が、通信を支える基地局自体が被災するケースです。
地震や台風により設備が損傷したり、停電によって電源供給が絶たれたりすると、基地局は機能を失います。
多くの基地局には予備電源がありますが、稼働時間には限界があり、復旧には時間がかかるのが現実です。その結果、被災地域では携帯電話が全く使えない、という事態も起こり得ます。
災害時に「固定電話」も安心とは限らない
携帯電話の通信障害が注目されがちですが、実は固定電話にも課題があります。
確かに固定電話は「安定した通信手段」として認識されることが多いものの、災害時には停電や設備被災の影響を大きく受けやすいという弱点があります。
たとえば、オフィスや家庭に設置されている固定電話回線が断線した場合、通信は完全に遮断されます。さらに、停電時には電力供給が絶たれ、電話機が動作しなくなるケースも少なくありません。
また、固定電話はその名の通り設置場所が固定されているため、避難や外出先での使用ができないという制約もあります。これでは、非常時に柔軟な連絡手段として機能しづらいのが現実です。
災害時に備えた「別の通信手段」が必要
携帯電話や固定電話に依存しすぎることは、災害時における通信リスクを高める要因になります。
企業や組織においては、非常時でも確実に連絡が取れるよう、クラウド型の通話手段や、BCP(事業継続計画)に基づいた通信インフラの整備が求められます。
- 「基地局が使えない」
- 「電話が混雑してつながらない」
こうした事態に備えるためには、どこにいても利用できる通信手段が欠かせません。
たとえば、インターネット環境さえあればスマホやPCで会社番号の発着信が可能なクラウド電話は、災害時の強力なバックアップになります。
クラウド電話が災害に強い理由
「クラウド電話は災害に強い」とされる理由は、以下のような設計上の特長にあります。
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| クラウド保存 | データがクラウドにあるため、端末や設備が被災しても他拠点から利用可能 |
| インターネット通話 | 固定回線に依存せず、地域限定の物理的被害に左右されにくい |
| モバイル対応 | スマホ・タブレットから通話・設定が可能。避難先や自宅でも利用可能 |
最大の課題は、インターネット回線への依存です。クラウド電話はクラウドサーバーを通じて通信を行うため、災害時にインターネット回線が途絶えると利用できなくなる可能性があります。また、停電が発生した場合、Wi-Fiルーターや関連機器の電源が失われ、クラウド電話システム全体が機能しなくなるリスクがあります。
ただし、多くのクラウド電話サービスでは、複数のクラウドサービスや地理的に分散されたデータセンターを活用することで、災害時のリスクを最小限に抑える工夫がされています。このような設計により、特定の地域でインターネット回線やデータセンターに障害が発生しても、他の拠点でサービスを継続できる冗長性を確保しています。
また、自動的に別のサーバーへ切り替える仕組みや、モバイル通信を利用した代替手段を提供するサービスもあり、通信の安定性を高めています。
災害時に利用可能な通信手段と特徴

災害時の通信手段として携帯電話や固定電話だけに依存することには、これまで見てきた通り、多くのリスクが伴います。そこで、携帯電話がつながらない状況でも事業を継続するために役立つ、代替通信手段や効果的なソリューションについて詳しく見ていきましょう。
SNSやインターネット通信手段
電話回線が混雑しやすい災害時でも、テキストベースの通信(SNS・LINEなど)は比較的つながりやすい傾向があります。
これは、通話に比べて通信容量が小さく、ネットワークへの負荷が少ないためです。
| 通信手段 | 特長 |
|---|---|
| SNS(X、Facebookなど) | 状況共有や安否確認に便利。多人数に同時送信できる |
| メッセージアプリ(LINE等) | 通話不可でもテキスト送信が可能な場合がある |
公衆電話の利用とその重要性
意外に思われるかもしれませんが、公衆電話は災害時に極めて有効な通信手段です。
携帯のバッテリー切れや輻輳時でもつながりやすく、自治体によっては大規模災害時に無料化されることもあります。日頃から最寄りの公衆電話の位置を確認しておくことが重要です。
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| 高い通信安定性 | 回線が独立しており、災害時も利用できることが多い |
| 無料利用の可能性 | 災害時に通話料金が免除されるケースがある |
特別な通信デバイス
企業や自治体、医療機関などでは、一般回線とは異なる通信手段を非常時用に備えているケースもあります。
| デバイス | 特長 |
|---|---|
| IP無線機 | ・インターネット経由で広域通信/GPS連携も可能 ・災害時の位置情報共有に有効 |
| 衛星電話 | ・通信衛星を使用。地上回線に依存せず通信が可能 ・通話料・端末コストが高額 |
これらは日常利用には向きませんが、緊急時に確実な通信手段としての信頼性は非常に高いため、BCPや防災対策の一環として導入を検討する企業・団体が増えています。
00000JAPANと特設公衆Wi-Fiの使い方
大規模災害時には、携帯電話各社が共同で「00000JAPAN」という無料のWi-Fi接続サービスを開放することがあります。パスワード不要で利用できるため、早急にインターネットに接続して情報収集や連絡を取ることが可能です。また、自治体や民間施設が特設公衆Wi-Fiを設置する場合もあり、避難所や公共施設などで複数の通信手段が確保される体制を整えています。
企業が事業を止めないために必要な「通信BCP」
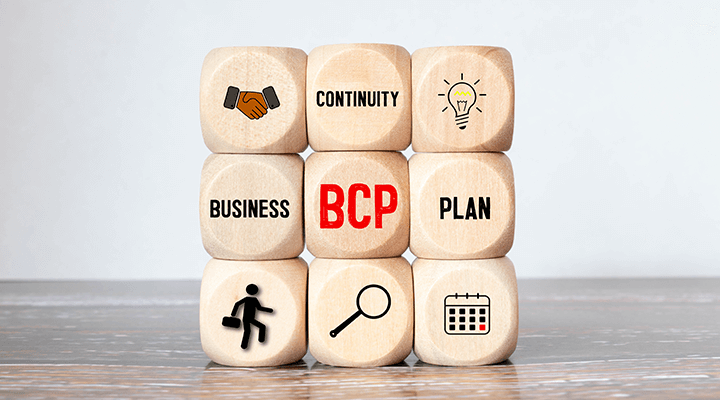
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策とは、災害や緊急時に事業を継続または迅速に復旧させるための計画や取り組みのことです。その中でも特に重要なのが、「通信手段の確保」です。
地震・台風・停電などによって、オフィスの固定電話や携帯電話が使えなくなると、顧客や取引先との連絡が断たれ、業務が大きく停滞してしまいます。その対策として有効なのが、インターネット回線を活用したクラウド型の電話システムです。クラウド電話であれば、特定の場所や設備に縛られず、災害時でもスムーズな業務継続が可能になります。
通信BCPは、企業の信頼を守るだけでなく、社員や関係者の安全と安心を確保するための“備え”でもあります。
Widefoneが提供するBCP対策
クラウド電話「Widefone」(ワイドフォン)は、災害時にも事業継続を支える柔軟で信頼性の高い通信ソリューションを提供します。スマートフォンを活用したクラウド型電話システムにより、オフィス外や災害時でも代表番号の着信や内線通話が可能です。これにより、事業の中断を最小限に抑え、迅速かつ効率的な対応を実現します。WidefoneのBCP対策がどのように役立つのか、詳しくご紹介します。
クラウド型で拠点間連携を強化
クラウド電話の最大の利点は、物理的な設備に依存せず、どこからでも通信が可能である点です。
インターネット回線さえあれば、オフィスが被災しても、別拠点や自宅から代表番号を使った発着信が可能になります。
たとえば本社が災害で機能停止した場合でも、支社や在宅勤務の社員が本社番号宛の着信を遠隔で受けることができるため、通信断絶による業務停止リスクを回避できます。
拠点間連携のクラウド活用例
| 状況 | クラウド電話の対応 |
|---|---|
| 本社が被災・停電 | 支社や在宅勤務者が代わりに代表番号で応答できる |
| 通常業務時 | 全国拠点で内線通話・転送がスムーズに行える |
| 地理的分散リスクの軽減 | データはクラウド上に保管、物理拠点に依存しない |
Widefoneを導入することで、災害時にも強い通信インフラを確保し、拠点間の連携を維持したまま事業継続が可能となります。
携帯回線に依存しない代替通信手段
Widefoneは、スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、050番号などの“予備用ビジネス番号”を持たせることが可能です。携帯回線が混雑や障害でつながらない場合でも、インターネット経由で安定した通話が確保できます。
安否確認や緊急連絡も、アプリからすぐに発信・着信が可能なため、通信断絶のリスクを減らし、スムーズな情報共有を実現します。
Widefoneの災害時通話イメージ
| 通信手段 | 状況 | 通信確保の可否 |
|---|---|---|
| 携帯電話回線 | 輻輳(混雑)や電波障害で不安定 | 利用不可の可能性あり |
| Widefone(IP通話) | インターネット環境があれば利用可能 | 代替通話手段として有効 |
加えてWidefoneは、上記のように災害に関するBCP対策だけではなく、携帯電話キャリアの大規模通信障害の備えとしても、大いに活用いただけます。日常使いが災害時のバックアップにつながるその理由を、過去の災害や障害をもとにご紹介している、以下の活用事例もあわせてご参考ください。
Widefone活用事例:見落とされがちな災害時の音声通信手段の備えは充分ですか?BCP対策にもWidefone
Widefoneと他社クラウド電話との比較
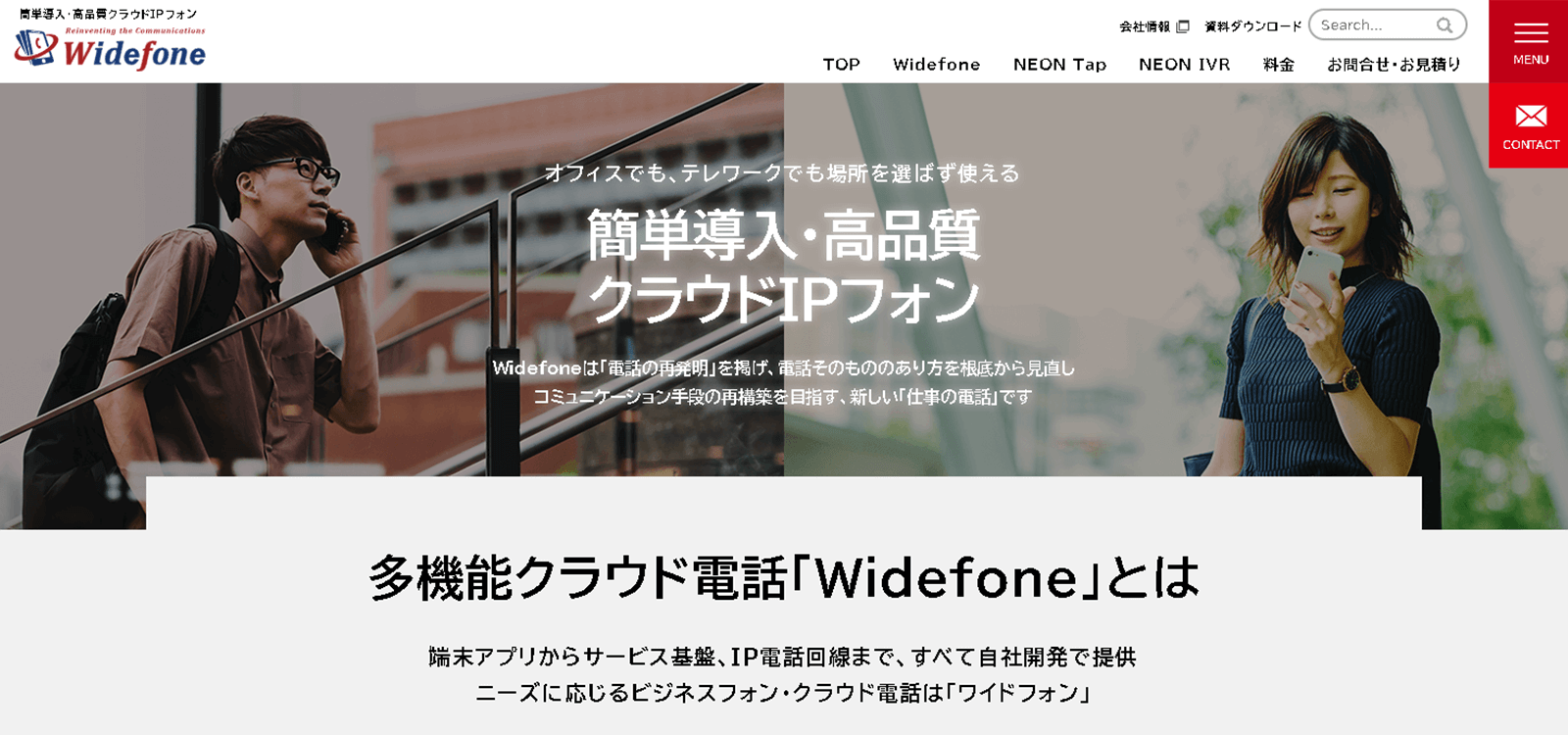
災害に強いと言われるクラウド電話ですが、提供サービスは複数あります。その中でWidefoneは他社にない以下のような特長を持っています。
- 専門性の高い通話アプリ
多くの同様製品が汎用的なプラットフォームをもとに設計されている中で、使いやすさを追求しゼロから設計したオリジナルアプリを提供しています。自社開発・自社運用サービスのため、お客様の声を反映したスピーディな機能開発が特長です - 豊富な機能
他社がオプションとして用意している「時間外スケジュール機能」や「不在着信メール通知機能」は標準機能として提供。オプションで選べる通話録音機能やSaaS型IVR機能も、お手軽な価格で提供しています。豊富な機能を手軽に使えることも、Widefoneの特長です - 導入と運用が手軽
予備用電話番号を持ちたいというご要望には、月額基本料金(900円)の費用対効果の高さも魅力の一つです。また、Widefoneどうしは通話が無料なので、社内の連絡や拠点間のやり取りがコストを気にせず行えます。
まとめと今後の災害通信への対応
災害に備え、そして実際に起こった際にどのように通信手段を活用し、情報を共有していくのか、最後に重要なポイントを整理します。
災害時通信では、多様な手段を事前に把握し準備しておくことが、回線輻輳や停電などのリスクを軽減する最善策となります。携帯電話や公衆電話、SNS、衛星電話などを状況に合わせて使い分け、安否確認や救援依頼を確実に行うための手順をあらかじめ取り決めておくと良いでしょう。通信事業者や自治体が行っている取り組みにも注目し、官民が連携して災害復旧を迅速化する動きに参加することで、社会全体の防災力が高まっていきます。
大規模災害はいつ発生するか予測が難しい一方で、通信インフラを守り支援する仕組みは日々進歩しています。今後も5Gや6Gなどの高速通信、AIやIoTを活用した被害最小化対策など、新しい技術が続々と登場するでしょう。私たち自身も災害時通信の基礎知識を身につけ、身近で使える手段を常に確認・アップデートすることで、万が一の状況にも慌てず行動できる態勢を整えることが大切です。
そして、災害時でも柔軟に対応できる通信手段として、クラウド電話の導入を検討することも有効です。その際は、高い柔軟性と経済性を兼ね備えたWidefoneを、ぜひ選択肢の一つに加えてください。
※機能や価格は公開日時点の情報です
※価格は税抜表示です



